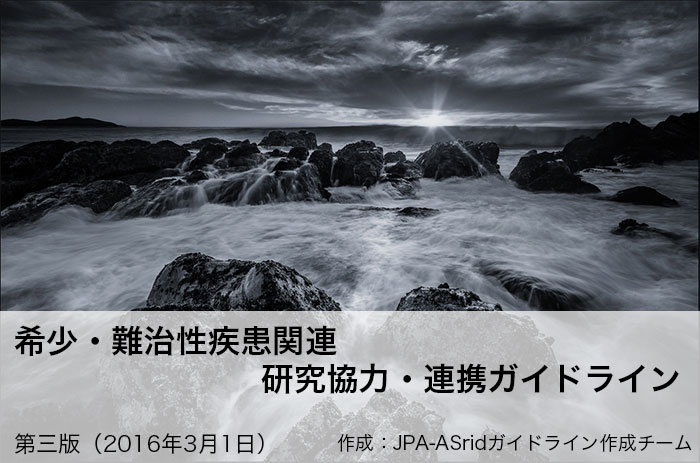
はじめに
本ガイドラインは、学術研究などに協力もしくは連携をおこないたいと考える患者会もしくは患者関連組織に向けて作成されたものです。現在既に行っている組織だけでなく、今後予定している組織にとってもわかりやすい内容となっています。このガイドラインを読んでいただき、研究協力もしくは連携に関する抵抗感を薄めていただくとともに、正しい姿勢で臨んでいただくことを期待しております。
また、2nd editionからは、研究者に向けた文章も追記しました。研究を直接実施する側が、協力・連携者もしくは対象者である患者・関係者への理解を深めるためにも用いていただくことができます。また、3rd editionでは、さらなる改訂をおこなうとともに、倫理に関する記述も追記しました。
作成グループは希少・難治性疾患(難病)関連患者会関係者です。そのため、本ガイドラインの第一対象者はこれらの方々が該当します。一部の記述については他の疾患関係者には該当しない箇所もあります。しかしながら、全体としては一般的な記載を心がけ、多くの方々にご理解いただけるような内容にいたしました。
本ガイドラインを作成するにあたっては、研究班に所属している研究者や、既に研究協力を実施している希少・難治性疾患(難病)関連患者会関係者に対して複数のヒアリング調査を行いました。ここに改めて感謝の意を表します。また、作成グループが2012・2013年度に実施したアンケート調査結果も参考にしております。
本ガイドラインには、本文に加えて参考資料の掲載サイトがリンクされております。本文はなるべく簡潔かつ平易に記載し、その上で更なる詳細情報を得たい方はリンク先を参照してください。
本ガイドラインは公開した段階で完成というわけではなく、これからも情報を付加・編集していくことを予定しております。皆様のご協力が、本ガイドラインをますます有益なものへと変化させることを期待しております。ご意見を是非お寄せください。
なお、内容は予告なしに改訂されることがあります。改訂する際にはバージョンを変更いたしますので、事前にご確認ください。
本ガイドラインは、本文をPDFバージョン(印刷して紙媒体で読むことが可能)とWebバージョン(インターネット上で読むことが可能)の両方で提供しております。PDFバージョンをご希望の方はこちらからダウンロードしてください
目次
1.研究協力・連携とは
1-1.本ガイドラインで述べる「研究協力・連携」とは
本ガイドラインでは、「患者会(もしくは患者個人)による研究協力・連携」の定義を「患者会(もしくは患者・患者家族個人)が、大学をはじめとした高等教育機関等が実施する学術研究に、「協力もしくは連携」という何らかの形で広義に参画し貢献すること」とします。
昨今、科学者自身が、「社会が科学に抱く期待」を理解し、その理解促進に向け尽力することが重要であるとされています。これにより、科学者「だけ」で研究を実施するのではなく、一般市民を含む科学者「以外」と様々な形で協力・連携するといった流れが大きくなっています。
協力と連携の違いは、どのように研究に関わるのかにより違います。前者は研究サイドからのリクエストによる受け身な形を、後者はより積極的な形を指します。どちらも大切な関係ですので、以降も両語を併記します。内容の詳細は 【2】研究協力・連携の種類 を確認してください。
研究協力・連携には様々な形があります。例えば研究内容を知るための勉強会を患者会が開催することも、研究内容を社会ならびに対象者に知らしめる行為という点では広義の協力といえます。
これらの行為によって、
- 研究を促進させる、
- 研究を世に知らしめる、
- 研究が正しい方向に向かっているかを確認する(結果的に導く)
などの効果が考えられます。
こういった協力・連携は、患者側からの要望によるものだけでなく、研究実施者側からの要望がある場合もあります。これは、上述のような研究を発展させていくことは研究実施者だけではなし得ないことも多いことの現れです。協力・連携の形は、今後ますます多様化していくことでしょう。言い換えれば、これらの多様性は研究実施者もこういった(広義の)参画を期待していることを指し、患者会もしくは患者個人でできることはたくさんあるということと同義であるといえます。
1-2.学術研究・研究班とは
学術研究と一口に言ってもその範囲は非常に広く、希少・難治性疾患領域の場合、基礎研究から応用研究、臨床開発研究に至るまで多岐にわたります。例えば、基礎研究実施者には理学・工学系研究者等も多く含まれますが、臨床開発研究実施者には医学系研究者が中心となることも多くあります。
国内の学術研究支援は、一般的には文部科学省・厚生労働省といった政府機関によりおこなわれます。研究者は、研究テーマや計画、新規性や発展可能性についての記載を含めた申請書類を作成し、審査を経て採択された後に、単年(1年間)もしくは複数年期間にわたって研究を実施します。
研究に関わる研究者数は、研究規模によって個人または複数の場合があります。複数の場合は、主に以下のような役割があります。
- 研究代表者:研究計画の遂行(研究成果の取りまとめを含む。)に関して全ての責任を持つ研究者。大学等の高等教育機関に属する研究者が着任する場合がほとんどです。
- 分担研究者:代表者と責任を分担して研究を実施し、研究費の一部を主体的に使用します。
- 協力研究者:研究に協力します。
呼称については、助成プログラムによって異なる場合があるので、応募前に対象とする助成プログラムを確認してください。なお、大型研究によっては事務局機能が存在し、一般的には研究代表者組織に属します。
1-3.希少・難治性疾患(難病)分野の患者(会)とは
国内に存在する希少・難治性疾患(Rare and Intractable (incurable) Diseases)の疾患群は約500から600あり(厚労省疾病対策課、2013)、個別疾患総数は6500種類に及びます(NIH Database, 2014)。
当該分野における日本の患者会は、個別疾患もしくは疾患群ごとに形成されている患者会と、主に都道府県ごとに設置されている難病連(Regional NANBYO center)、それらをとりまとめる協議会やネットワークによって構成されています。主な構成員は患者もしくはその家族であり、会によっては医療関係者(Healthcare Professional)も参画しています。
希少・難治性疾患は、患者数が少ない・関連医療関係者や研究者などが少ない・疾患の解明が十分にされていない・治療診断が確定されていない・市場規模が小さく創薬開発に着手できない、など、様々な「ない」が存在するのが現状です。そのような中で、疾患ごとに存在する患者会・家族会をはじめとする患者団体が研究に協力する、もしくは研究者と連携していくことは、当該領域の研究を行う上で大きな推進力となることが予想されます。
患者会の活動内容、特に研究との関係についてより詳細を知りたい方は、参考文献にある報告書をご覧ください。
1-4.研究者ー患者(会)間の連携の重要性
国内の患者会は、患者同士の交流・情報交換を目的として設立されたものが多く、また当事者や家族のみで構成されているものも多数存在します。そのため、以前は研究に協力するイメージをもつことが難しいと感じる患者関係者も多く存在しました。しかしながら、昨今では病態解明や治療診断確立、創薬開発の重要性は広く認知されており、それらの推進に向けた活動をおこなう、もしくは希望する患者会も増えています。
研究者にとっても、この傾向は歓迎すべきことでしょう。対象者である患者サイドが研究に協力・連携することは、患者のみが有する知見の提供や研究への理解促進につながり、最終的には研究自体の推進力にもなるからです。
患者会には、複数の患者・家族らの知見が集結しており、また団体として内部の意見を集約したり外部情報を発信したりする能力も備わっています。研究者(研究班)が対象者側の協力・連携先として患者会を選択することはごく自然な流れです。
研究者ー患者(会)間の連携をするうえで重要なのは、「同じ方向に向かって進む」ための「知識の共有」ならびに「相手への尊重」です。これらが十分になされていない場合、せっかくの連携もうまくいかない場合があります。研究者側は必ずしも研究のプロではない患者側に十分に説明責任を果たし、丁寧な説明をおこない、理解を得ていく必要があります。また患者側も、「協力(連携)させていただく」「「協力(連携)してやる」といった極端な対応ではなく、「研究主旨を理解し気持よく協力(連携)する」ことが大切です。
参照
- 一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会(Japan Patients Association)
- (難病分野唯一の協議会であり、37の難病連および49の個別患者会が参加している(2015年12月現在))
http://www.nanbyo.jp/ - 認定NPO法人 難病のこども支援全国ネットワーク
- (親の会活動支援事業を実施し、56の団体が参加している(2015年12月現在))
http://www.nanbyonet.or.jp/
参考文献
- 研究分類
- http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/seisaku/haihu03/kanazawa6.pdf
- 研究者の種類について(科研費ハンドブック)
- http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/15_hand/data/kakenHB1106A5.pdf
*なお、一般的に政府機関に研究を申請する場合には、研究代表者ならびに分担研究者は応募資格を有していないと応募できません。事前に応募資格条件を確認するようにしてください。
- 患者支援団体等が主体的に難病研究支援を実施するための体制構築に向けた研究(略称 JPA研究班)
- http://www.nanbyo.jp/kenkyu/index.html
- 患者会と研究班間の研究協力に関する現状および意識に関する実態調査
- http://www.nanbyo.jp/kenkyu/hokoku/h1.html
2.研究協力・連携の種類
研究協力・連携には様々な種類があります。ここでは主な種類を紹介します。
| 患者・患者会が関わる (研究)協力の種類 | 内容 | 患者(会)側メリット | 研究者(班)側もしくは 医師側のメリット |
|---|---|---|---|
| アンケート回答・実態調査回答 |
・疾患や居住地域別といったいくつかの分類による日常生活についての調査回答 ・患者の生活実態調査 ・治療・診断などに関するアンケート調査といった各種調査への回答 |
・疾患をかかえた患者がどのような生活をしているか、患者が地域でどのような暮らし方をしているのか、などの調査に参加することにより、自分の状況を直接回答に反映させることができる ・普段は言いにくい意見などを届けることができる |
・医師に言いにくいことなどを明確にして提案できる ・患者がどのように思っているのかを、知ることができる ・患者の臨床情報だけでなく、日常情報に関する患者の声も知ることができる |
| 疫学情報収集 |
・疫学研究で使用する基礎情報の提供 |
・情報を提供することで、疾患の原因や予防法、治療の有効性などの検証に役立てることができる |
・疾患の成因を探り、疾患の予防法や治療法の有効性を検証することができる ・環境や生活習慣と健康とのかかわりを明らかにすることができる |
| 生体試料提供 |
・血液や尿、組織など、患者身体の試料を提供する |
・血液、尿などを提供することにより、疾患の原因を究明して、治療にいかしてもらうことができる ・通常の検査時に追加で協力できる |
・患者本人の試料を提供してもらい、分析研究することにより、対象疾患の原因の究明、治療法の確立に向けた研究することができる |
| 臨床試験・治験へのデータ協力 |
・ヒトを対象として新しい治療薬の有効性および安全性を調べる試験への協力もしくは個人情報提供 |
・個人情報を提供することにより、より効果が高く安全性も高い治療薬の開発に協力できる |
・政府の承認を得るために必須の試験を経て、一般社会に新しい治療薬を提供できる ・患者会と連携することで、より多くの試験参加者を集めることができる |
| 研究班への直接参加(実施者・分担者等) |
・研究班に具体的に参加し、研究発表や報告書を作成する |
・患者・関係者が有している知識・知見を班内で研究の一部として提供できる ・患者・関係者の視点から研究(の一部)に関わることができる ・研究者側と日頃から交流を深めることができる |
・患者・関係者に、より責任のある貢献を依頼することで、患者視点踏まえた研究を実施することができる ・患者に対する調査を実施する際、アンケート調査など、患者ならではの項目設定や分析結果が収集できる |
| 班会議傍聴・発表 |
・班会議を聴講する。もしくは班会議内で発表する |
・班会議にて直接研究発表や質疑応答を聞くことで、研究の進捗状況を理解することができる ・研究者に直接質問をすることができる ・自ら発表することで患者視点の考えを直接研究者に届けることができる |
・研究対象者でもある患者に直接研究内容を伝えることができる ・その場で意見交換を行うことで、不必要な誤解や理解不足を防ぐことができる ・直接対話の中から新たな研究アイデアを見出すことができる |
用語解説
- 疫学研究
- 疫学研究は、疾病などの事象の頻度や分布を調査し、その要因を明らかにする科学研究を指します。疾病の成因を探り、疾病の予防法や治療法の有効性を検証し、又は環境や生活習慣と健康とのかかわりを明らかにするために、疫学研究は欠くことができません。医学の発展や国民の健康の保持増進に多大な役割を果たしている研究です。疫学研究では、多数の研究対象者の心身の状態や周囲の環境、生活習慣等について具体的な情報を取り扱います。また、疫学研究は医師以外にも多くの関係者が研究に携わるという特色を有しています。
- 臨床研究(治験)
- 患者に協力してもらい、病気の原因の解明、病気の予防・診断・治療の改善、患者さんの生活の質の向上などのために行う医学研究を指します。新しい薬が政府の承認を得て一般の診療で使えるように、客観的なデータを集める目的の臨床研究は、別に臨床試験あるいは「治験」と呼びます。
参考文献
- 疫学研究に関する倫理指針
- http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/ekigaku/0504sisin.html
- 治験とは (日本製薬工業協会ウェブサイトより)
- http://www.jpma.or.jp/medicine/shinyaku/chiken.html
- 臨床研究とは
- http://www.ccr.med.keio.ac.jp/patients/about_clinical/
3.研究協力・連携を開始するには
3-1.患者側のアクション
- 研究および研究者を知ろう、つながろう
- 自分達の病気について研究している研究者、研究班を調べてみましょう。例えば、難病情報センターウェブサイトの中の「サイト内検索」に病名を入れて検索したり、研究班のリストから探したりすることができます。または主治医の先生に尋ねてみるのも良いでしょう。
- 研究者、研究班がわかったら、連絡を取ってみましょう。研究者側に会のパンフレットや会報などを送ることや、ウェブサイトなども通じて自分達の活動内容をお知らせすることも効果的です。患者会として連絡をとることで、より公式な回答を得ることもできます。
- 研究協力・連携の内容を検討しよう
- 研究者側が話す研究の目的ならびに要望を聞き、どのような研究協力・連携ができるか考えましょう。多くの研究者は真摯に研究に向けて取り組んでいます。彼らが目指す目標を理解しようと務める姿勢も大切です。可能であれば、実際に会った上で質問すると、より本音を教えてもらえます。
- 最初に、研究者側から、これまでの研究の趣旨や具体的な内容について患者や家族が理解できるように説明していただきましょう。わからない場合に質問をしても問題ありません。わかった「ふり」は、その後の関係構築に影響を及ぼすことがあります。納得のいくまで説明を受けましょう。
- 一方で、研究者側があなたの患者会について十分な知識を得ていない可能性があります。そのため、会の活動内容や自分たちの患者会に何の病気の人が何名くらいいるのかなどを伝えましょう。先ほどの反対で、患者側がわかりやすく説明することを心がけましょう。
- 希望と現状を考慮したうえで、具体的にどのような協力・連携ができそうか、話し合いましょう。その場合、患者側にどのような責任や負担が生じるかについて、きちんと確認しましょう。
- 連携する場合には、納得がいくまでやり取りを重ねることも大切です。例えば分担研究者として参画する場合、研究がひとたび開始されるとその研究に関する責任の一端を担うことになります。意見交換を頻度高く実施することで、研究者間の信頼関係も生まれ、よりスムーズに研究が実施できます。
- 患者会内部で話し合って結論を出しましょう
- 具体的にどのような協力・連携を求められているのか、また自分たちの希望を確認したうえで、できることを検討しましょう。可能であれば、研究者側から役員会に来ていただいて、内容について説明していただくことも効果的です。
- 研究協力・連携によるメリットを検討しましょう。治療法の開発や患者の日常生活の向上にどのように役に立つのか、などです。研究はすぐに結果が出るものばかりとは限らないので、今の取り組みが将来どのような結果につながりそうか、短期的だけでなく中長期的な視野を持って考えてみましょう。
- 一方で、デメリットもよく検討しなければいけません。会にとって人的、経済的、時間的な負担がどの程度あるのか、それを実際に実施できる体制かどうか、また協力する患者の負担はどんなものかを具体的に考え、検討しましょう。
- メリット、デメリットをよく踏まえた上で、研究協力・連携を実施するかどうか、またどのような内容にするかを決定して研究者側に伝えましょう。
3-2.研究者側のアクション
- 患者会および患者とつながろう
- 自分達の対象疾患の患者会を調べてみましょう。現在は多くの患者会がウェブサイトを有していますので、検索エンジンで調べることで簡単に探すことができます。海外の患者会情報を得たい場合には、WINPR(希少疾患患者会インデックスサイト)などが有益です。
- 患者会への連絡は、メールが一般的ですが、患者会によっては電話やファクスのみを受け付けている場合もあります。また患者会規模によっては返信が遅い場合もありますので、題名に研究者(班)からの連絡であることを明記することが大切です。
- 研究協力・連携の内容を提案しよう
- 研究者(班)の内容を丁寧に説明したうえで、研究者側の提案を率直に伝えましょう。獏とした段階であっても、患者視点からの意見を聞いてみることも有益かもしれません。内容については、相手は研究のプロではないことを今一度自覚したうえで、文字資料ではなくプレゼン資料を作成すると患者側の理解が進みます。補助資料等があれば、患者会内で検討する際に役立ちます。
- 患者側は研究者からのコンタクトということで緊張している場合も多いので、実際に会うことをおすすめします。その際、患者会の活動についても率直に聞くことができると、患者会の方向性や現状を知ることができ、双方の理解が深まります。
- 患者のために研究をしてやる、という姿勢ではなく、相手側に上下関係を感じさせないふるまいを心がけましょう。
- 具体的に患者側がどのような協力・連携ができそうか、話し合いましょう。その場合、患者側にどのような責任や負担が生じるかについて、きちんと説明しましょう。
- 患者側は、患者会として検討する場合には時間を要する可能性があります。後日追加質問等を受ける場合もありますので、その場合には丁寧に対応しましょう。
参考文献
- The Montreal Statement on ResearchIntegrity in Cross-Boundary Research Collaborations(境界を超えた共同研究における研究構成に関するモントリオール宣言)
- http://www.researchintegrity.org/Statements/Montreal%20Statement%20English.pdf
- 難病情報センター
- http://www.nanbyou.or.jp/
- 一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会(JPA)
- http://www.nanbyo.jp
- 特定非営利活動法人 ASrid (アスリッド)
- http://asrid.org/
- WINPR(希少疾患患者会インデックスサイト)
- http://winpr.asrid.org/ja
4.研究協力・連携の過程
研究協力・連携を実施することが決まったら、次の基本プロセスを参考にして進めていきましょう。
- 具体的に打ち合わせをおこないましょう
- 何をいつまでにどのように行うか、研究側とよく打ち合わせましょう。研究期間内に予定されている各種会議開催日程(説明会や報告会など)、調査が必要な場合には調査時期、報告書の発送時期などを確認します。患者会の機関誌発行や総会、交流会等と合わせて実施できるものがあればお互いの手間と費用を減らすことができます。
- 研究内容が書かれている資料を用意し、説明を容易にできるよう準備をしておきましょう。
- 問い合わせがあった場合の窓口担当者と、質問への回答内容や分担などについて打ち合せておきましょう。
- 経費についても検討しましょう。例えばアンケート調査票の郵送料や返送料、会議やインタビューの交通費、会議室料など、必要な経費を研究側と患者側のどちらが負担するか、支払い方法をどうするかなどを確認しましょう。
- 情報の取り扱いについて確認しましょう
- 会員の情報(名前、病名、住所その他)をどう扱うかの取り決めをしましょう。名簿を研究者側に提供する形にするか、名簿は会が管理して対象者に研究協力を依頼する形にするか、などについても話し合いましょう。
- 調査によって得た情報をどう取り扱うかについては、口頭だけでなく文書の形で取り決めを行いましょう。
- 患者の情報を集める研究者側だけでなく、協力・連携する患者側にも守秘義務が発生します。守秘義務の内容、範囲を事前に明確にして、責任を持って研究協力・連携を実施しましょう。
- 患者会側対象者へ説明をしましょう
- 会員への説明と協力依頼をする際には、正確に伝えることが重要です。研究者側に概要を簡潔に1~2枚にまとめていただき、その用紙を利用して会員に説明したり、機関誌や調査用紙と一緒に送ったりすると良いでしょう。
- 対象を限定する場合には、その理由などについてもあわせて記載しましょう。
- 説明の仕方は、あなたの会の状況に応じて検討しましょう。(対面式説明会開催、患者会メーリングリストなどを利用、理事会などの機会を利用、など)
- 場合によっては研究者(班)側に協力を仰ぎ、スムーズに説明ができるように工夫しましょう。
- 実際に研究協力・連携を実施しましょう
- 取り決めたスケジュールに従って、実際の研究協力・連携を実施します。必要に応じて随時、研究側との意見交換の場を作り、会員からの疑問、要望、苦情等にはできるだけ迅速に対応できるようにしましょう。
- 成果を報告しましょう
- 成果の報告の仕方には、研究発表や学術論文投稿、班会議などでの発表や報告書作成など様々な方法があります。研究者側と相談して報告の仕方を決めましょう。
- 患者会ウェブサイトなどで報告する際には、事前に研究者側に内容の確認をしてもらいましょう。【6】研究協力・連携について気をつける点 も確認してください。
5.研究協力・連携を続けていくには(患者会向け)
研究の内容によっては短時間で成果がでるとは限りません。もちろん患者にとっては一日も早く結果の出ることが望ましいのですが、長期間の研究協力・連携の継続によってより良い成果を生む場合があります。研究協力・連携の継続にはどのようなことが必要でしょうか。皆さんもぜひ考えてみてください。
- 研究者側との関係性:お互いの信頼関係を構築していくよう努力しましょう
- 長期にわたり協力・連携を継続させるためには、研究だけのお付き合いではなく、患者会の活動等についても理解していただく必要があります。そのためには研究者を患者会の総会に招待したり、意見交換会や勉強会を開催したり、お互いの思いを率直に届けることも大切です。
- 患者会が社会から見て理解されやすい存在になれば、もちろん社会からの協力も得やすくなるでしょう。研究側に対してだけではなく、社会に対して幅広く患者会側からの情報提供を積極的に行うことにより、お互いの関係はより円滑により深くなると考えられます。
- 研究者側からの患者会に対する成果報告会を定期的にぜひ開催していただきましょう。研究者側にすべてをお任せするのではなくて、研究の進捗状況を患者会側もある程度は理解しなければ、長期間の協力・連携は目的を見失ってしまいます。
- 研究者側との信頼関係はお互いの人間関係を深めるだけでは構築できません。研究にはある一定の社会的ルールが存在します。【6】研究協力・連携について気をつける点 にも記述がありますので、ルールを確認してください。
- 患者会内部の役員間で慎重に検討しましょう
- 研究協力・連携が始まった当初は具体的な研究の内容までは患者会側はわからず、患者会役員からの意見として「まずは始めてみよう」という状況も考えられます。しかし、その活動を継続するとなると、研究協力・連携の必要性について患者会内部の役員間の同意や確認が必要になってきます。
- それでは、研究協力・連携を継続するためには、どのような判断基準があるでしょうか。一例として、患者会への研究のメリット、研究の将来性、個々の患者への成果の還元、研究外のことも含めたインセンティブ(動機づけ)などが考えられます。
- 一方で、患者会内部だけで研究のメリットや将来性を正しく議論することは困難です。場合によっては研究者側からの説明が必要になることもあります。研究側との関係性を深める意味でも、役員会や理事会において、研究側からの説明を受けることも検討する必要があります。
- 研究協力・連携が進んでいくと、多くの研究側からの申し出がくる可能性も出てきます。すべての研究に協力できる状況ではない場合に、取捨選択のための判断基準も必要になるでしょう。しかし患者会内部だけの判断では難しい場合には、顧問の先生など第三者的な専門家の意見も参考になるかもしれません。患者会に協力的な有識者を徐々に増やしていくことも、研究協力・連携を続けていくポイントの一つです。
- 会員への呼び掛けや説明をおこないましょう
- アンケートの回答、実態調査の依頼、臨床試験・治験の協力など、研究協力・連携には個々の会員の協力も必要になってきます。人によっては自分のデータが研究材料になることを嫌う方もおられるでしょう。個人情報の保護はもちろんのこと、研究協力・連携の継続には会員の理解も不可欠になります。
- 例えば、臨床試験(治験)は治療薬の開発のためには不可欠なことです。患者の協力なくして医療の発展は望めません。しかし、研究の必要性は認めながらも自身との関わりについてはとても遠い存在であることは確かです。研究の意義などを会員に伝えていくことも患者会の役割ではないでしょうか。
- 会員への呼び掛けには機関誌やメールの活用が考えられますが、該当者の選定能力や迅速な対応能力も研究側との信頼関係を高める大切な要素です。そのためには、データベースによる情報の整理も必要になるかもしれません。研究面だけではなく、情報のデータベース化は患者会にとって大切な財産になると考えられます。
- 患者会の基礎体力の充実をはかりましょう
- 医療の発展のために患者会がどのように貢献できるかは、患者会の存在意義として非常に重要です。ただし、研究協力・連携が患者会の役割のすべてではありません。人的に、時間的に、経済的に、研究協力・連携にどの程度の労力を使えるかを考えなければ、長期に渡る継続は不可能です。
- 例えば、アンケートの回答や実態調査の依頼がきても、実際には労力がなければ対応できません。特に継続的な事業の場合には、研究側に金銭的補助の確認も必要です。患者会の基礎体力の充実は必要ですが、患者会からの持ち出しだけでは継続は不可能です。
- 患者会の基礎体力がついてくれば、患者会主導の研究が可能になるかもしれません。患者会の具体的なニーズの実現のために患者会がお金を取ってきて、専門家と共同研究することもあり得るということです。例えば、生活実態調査について研究者を巻き込んで行えば、より正しく詳しい調査結果を導き出せるでしょう。
- 国内、海外の成功事例を知りましょう
- 研究協力・連携の問題点や課題を克服するために、患者会同士の意見交換も有用と考えられます。アンケートの調査項目など具体的な部分についても、他の患者会の活動は非常に参考になります。成功事例を増やすためにも、患者会同士の連携を深めていくことも大切です。
- 海外の患者会では、医師や研究者と患者が協力して新しい治療や診断基準を作っていくような動きが増加しています。国内のみならず、海外の研究協力・連携の成功事例を共有することで、より良い成果を出すことができるようになるでしょう。
希少・難治性疾患は「病気」です。解明を試みている研究者がいる限り、「治す」ために尽力している人の存在を知り、「治る」ためにできることを一緒に考えていきましょう。
参考文献
- Rare Disease International (なお、希少・難治性疾患(難病)患者会の方が海外の研究者にコンタクトをとりたい場合は、NPO法人 ASridへご連絡いただければ可能な限り対応いたします。)
- http://www.rarediseasesinternational.org/
6.研究協力・連携について気をつける点
- 利益相反・研究不正について
- 利益相反という言葉を聞くと、多くの方が「難しそうだな」と思うのではないでしょうか。厚労省の指針によると「利益相反とは、具体的には、外部との経済的な利益関係等によって、公的研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる、又は損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されかねない事態をいう。公正かつ適正な判断が妨げられた状態としては、データの改ざん、特定企業の優遇、研究を中止すべきであるのに継続する等の状態が考えられる。」と定義されています。
- 利益相反というと、金銭的な意味合いだけを想定しがちですが、患者としては責務相反も念頭に置く必要があります。責務相反とは、「兼業活動により複数の職務遂行責任が存在することにより、本務における判断が損なわれたり、本務を怠った状態になっている、又はそのような状態にあると第三者から懸念が表明されかねない事態」を指します。例えば、患者会の運営に研究者を関与させたり、自分たちの患者会出版物をやみくもに推薦したりすることも、適切な研究の実施という本務に対する責務相反だと判断される場合もあります。また、自分の疾患に関係する研究の倫理審査や研究評価に関与する可能性もありえます。自分たちが特に意識していないことであっても、研究という場においては相反だと指摘される可能性はゼロではありません。参考文献などを事前に参照し、公正な視点を持って研究に参画してください。
- 利益相反(責務相反)については、現在では利益相反委員会(倫理審査委員会)を組織として立ち上げることが求められています。しかしながら、患者会の規模によっては、自前でこういった組織を立ち上げることが困難な場合もあるでしょう。その場合は、事前に研究者側に相談し、審査体制を確保しておくことが大切です。
- 研究不正には捏造、改ざん及び盗用などがありますが、特定疾患領域の発展を願うあまり、患者会の立場から恣意的・選択的にデータを提供することは捏造や改ざんにあたるおそれがあります。
- なお、研究の実施にあたっては、法令やルールの遵守が必要ですが、これらは年々変化しています。文科省・厚労省のウェブサイトなどを確認し、最新の知識を得るようにしてください。
- インフォームド・コンセントについて
- 厚労省の指針によると、インフォームド・コンセントとは「被験者となることを求められた者が、研究者等から事前に臨床研究に関する十分な説明を受け、その臨床研究の意義、目的、方法等を理解し、自由意思に基づいて与える、被験者となること及び試料等の取扱いに関する同意」を指します。生命倫理の議論の基となっている世界医師会の「ヘルシンキ宣言」には、「研究の目的がどれほど社会にとって重要なものであろうとも、その研究が被験者の尊厳や人権を侵害するものであってはならない」と名言されていますが、インフォームド・コンセントはこの「人格の尊重」を守るために重要なプロセスとなります。
- 「人」を対象に研究を実施する場合、研究実施者は対象者からインフォームド・コンセントを得る必要があります。つまり、患者サイドが研究の目的ならびにその中における自分(たち)の立場を理解し、参画を合意することそのものが、「研究者がインフォームド・コンセントを得る」ということなのです。研究者側も様々な工夫を重ねてインフォームド・コンセントを実施しますが、それでも充分に理解できない可能性は否めません。丁寧かつ適切な説明を得るためにも、是非研究実施者との継続的な信頼関係を上手に構築してください。また、将来的に参加者の意思や研究内容が変化する可能性もあるため、合意の撤回や新たなインフォームド・コンセントを取得する機会ができるかぎり与えられていることが大事です。
- 成果の取り扱い
- 研究側からの患者会に対する成果の公開・報告は必要ですが、研究である以上は患者会側にも守秘義務を伴う場合があるという理解が必要です。また場合によっては、患者会へはすべてを開示できないこともあると思われます。お互いの信頼関係を保ちながら、研究成果を最大限に活かすためには、研究に関する事前の丁寧な説明が不可欠です
- 特に患者会側が成果を開
以下に検討すべき点をまとめました。事前に研究班側と話し合っておくようにしましょう。
- 研究成果の取り扱いを含む契約内容について、一定のルールを定める
- 患者会側もそのルールに則り、研究成果を取り扱う
- 研究成果の帰属や守秘義務等を事前に明確にしておく
- 患者側も研究に参加しているという意識啓発により適正な行動が必要です。
- 患者会として関わるか、個人として関わるか、を意識しましょう
- 患者会として関わる場合は、組織(団体)として協力・連携となるので、当然組織に対して責任が生じます。参画する人を選ぶ際にも、組織としての方向性を説明する必要がありますので、事前に検討しておきましょう。また、発言の際には、会としての発言であることを十分に意識しておこないましょう。患者会の中で担当者を決定した後も、その人だけに任せるのではなく、協力内容、発言内容に会として気を配りましょう。
- 個人として関わる場合は、すべてが個人の責任となってしまう可能性がありますので慎重に対応しましょう。わからないことがあれば、研究者側に事前に問い合わせることも必要です。患者会が既にある状態で個人として関わる場合には、患者会として関わる場合とどちらが適切かを考慮し、必要に応じて患者会側に確認を取るようにしましょう。
- 患者本人が関わることに同意するか、患者家族ら関係者が同意するか
- 小児患者や意思決定が困難な患者の場合、本人ではなく家族が研究に協力したいと思う場合があります。患者自身と家族の意見は必ずしも同一ではないことを念頭に置きつつ、患者との対話に努めましょう。
- 研究遂行には時間がかかるということ、また成功だけでなく失敗の可能性もあることを十分に理解しましょう。
- 新薬は、長い研究開発期間をかけて新しい成分の有効性・安全性が確認された後、国の承認を受けて初めて発売されます。研究開始から販売開始までの期間は 10年とも15年とも言われており、とても長い期間を必要とします。
- 専門家によると、ヒトでの臨床試験に 100個の候補化合物が入ってきたとしても、最終的に「くすり」になるのはわずか 8個にすぎません。また、臨床試験前には多くの前臨床試験(実験動物を用いた in vivo試験や、試験管の中〈 in vitro〉の試験)が行われており、候補化合物が選ばれる確率は 1/3000程度です。さまざまなデータの裏付けに基づいて開発を進めているにもかかわらず、 8%しか成功しないのが医薬品開発の現状です。
- 個人情報保護について
- 個人情報をどう保護するか、については、インフォームド・コンセントの重要な一項目です。本項目についてはは、平成28(2016)年に改正が予定されているため、第四版にて記載いたします。
参考文献
-
*利益相反についてさらなる詳細を知りたい方は、以下の書籍を参考文献として用いて下さい。
日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会 編、科学の健全な発展のために —誠実な科学者の心得−、丸善出版、2015 - 研究活動の不正行為及び研究費の不正な使用について ガイドライン関連資料集
- http://www.jst.go.jp/researchintegrity/shiryo/collectiondoc.pdf
- 厚生労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest:COI)の管理に関する指針(平成20年3月31日科発第0331001号厚生科学課長決定)
- http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/rieki/txt/sisin.txt
- 厚生労働省、臨床研究に関する倫理指針、平成20年7月31日全部改正
- http://www.jst.go.jp/announce/rinri/shishin_rinri.pdf
- ヘルシンキ宣言(日本医師会ウェブサイトより)
- http://www.med.or.jp/wma/helsinki.html
- 創薬とは
- 製薬協ウェブサイト内
- http://www.jpma.or.jp/about/issue/gratis/guide/guide12/12guide_06.html
- くすり研究所
- 製薬協ウェブサイト内
- http://www.jpma.or.jp/junior/kusurilabo/
さいごに
本ガイドラインは、患者および患者関係者である作成グループが約2年間にわたって患者会調査・分析を行う過程で必要性および重要性を感じ、作成したものです。
このガイドラインは完成していません。また、一部の記載は未完成の箇所もあるかと存じます。しかし、本ガイドラインを読んで頂き、患者会が自分たちの使命のために研究班と奮闘するときにぶち当たるであろう苦労を、事前に少し覚悟してもらうだけで結果は相当違うのではないかと思います。何もわからないまま足を踏み入れるよりは、イメージだけでも考えなければいけないことを提示することで、研究者とのコミュニケーションが円滑になったり、言葉が通じ合ったりするができるようになるかもしれません。その結果、双方の信頼感は数段高まり、良好かつ前向きな協力・連携ができる可能性も高くなります。
今後も継続して内容の改訂・追記をおこなっていきます。皆さんからの意見を踏まえ、わかりやすい説明を心がけながら、より良いガイドラインを作成していきたいと考えていますので、今後もよろしくお願い致します。
ガイドラインプロジェクトチーム紹介・問い合わせ先
ガイドラインプロジェクトチーム
- 大黒宏司(一般社団法人 全国膠原病友の会、一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会)
- 永森志織(特定非営利活動法人 難病支援ネット北海道、一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会)
- 森幸子(一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会,一般社団法人 全国膠原病友の会)
- 西村由希子(特定非営利活動法人 ASrid, 一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会、 東京大学)*ガイドライン作成責任者
- Special Thanks to; 岩崎匡寿(ASrid) and Crimson Interactive Pvt. Ltd.
本ガイドラインについて
- 本ガイドラインは、以下の研究の一環として作成いたしました。
第一版:「患者支援団体等が主体的に難病研究支援を実施するための体制構築に向けた研究」(厚生労働科学研究費補助金、平成 24-25年度)
第二版:「難病患者への支援体制に関する研究」(厚生労働科学研究費補助金、平成26年度)
お問い合わせ先
https://asrid.org/contact (Yukiko Nishimura)